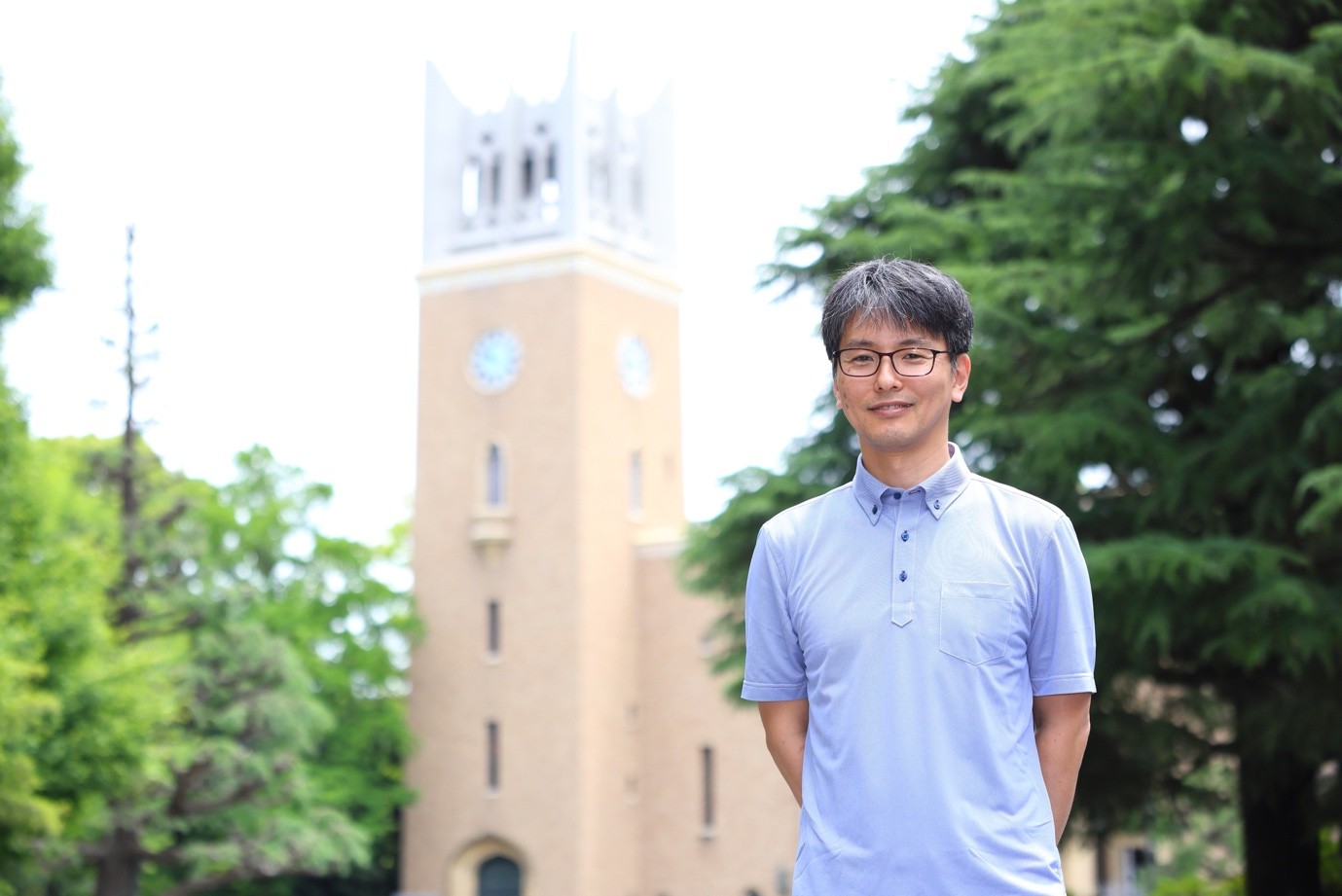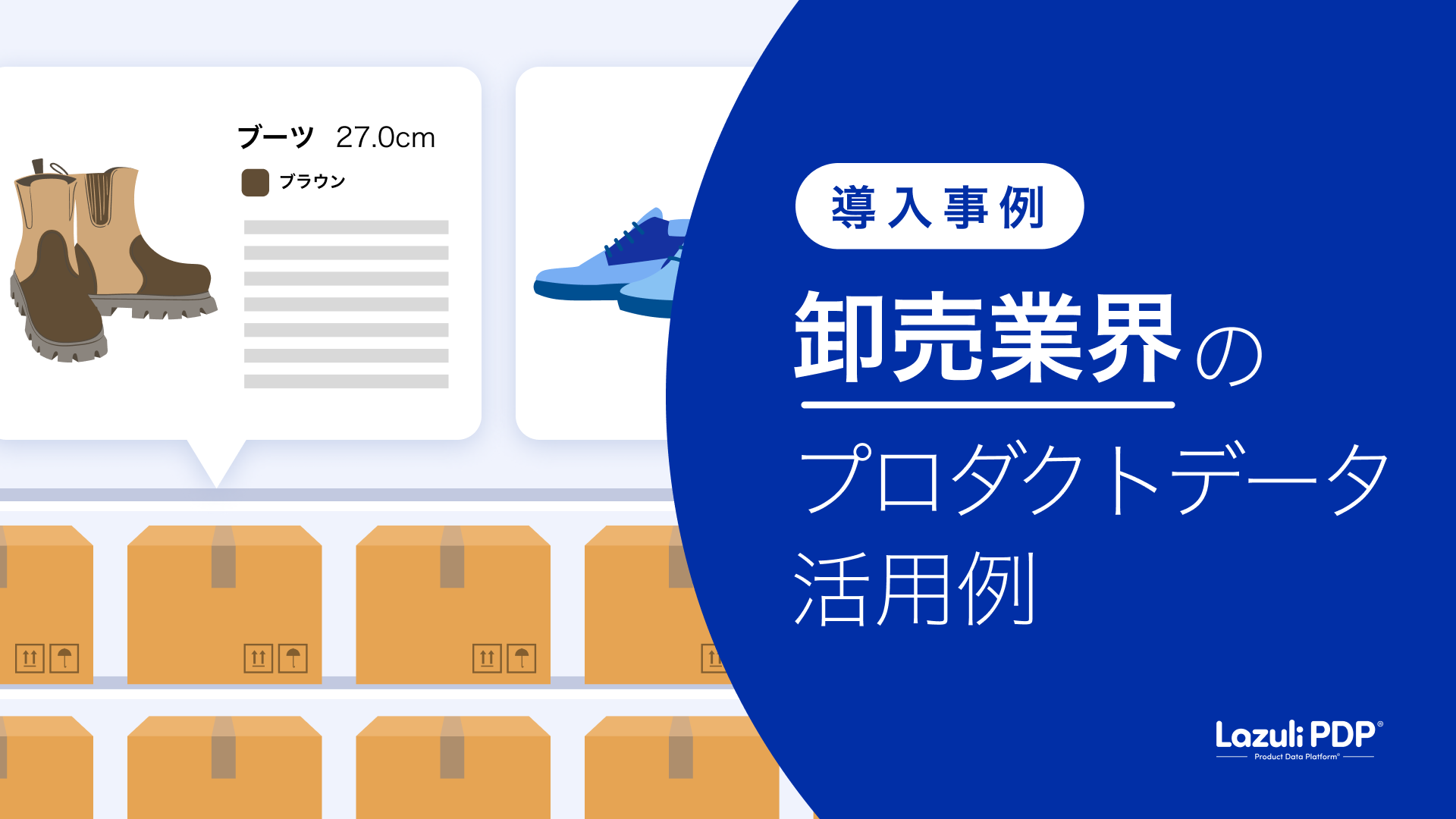購買行動がオンラインへシフトするなか、ECにおける商品の拡充は小売業者様にとって喫緊の課題です。品ぞろえの充実は重要な要素ですが、多くの場合、商品情報の入力が取り組み推進の障壁となります。ビックカメラ様は、総合通販サイト「ビックカメラ.com(ビックカメラ・ドットコム)」の商品点数を急拡大するなかで、Lazuli PDPを導入しました。株式会社ビックカメラ執行役員 EC事業部長 兼 株式会社ビックカメラ楽天代表の畑中 英治氏、同EC事業部係長の井東 紺氏に、導入の経緯と展望をお聞きしました。
——畑中さん、井東さんのこれまでのご経歴、現在のお役割について教えていただけますでしょうか?
畑中氏:2003年にビックカメラに入社し、9年間店舗で接客業務を中心に担当しました。2012年に資本提携したコジマへ出向すると、半年で本部に配属され、全国店舗の業務改善、システムの統合や、物流を経験します。2018年、ビックカメラに戻り、グループ全体の物流統合や、物流拠点のロボティクス導入に取り組みました。2024年問題(ドライバーの労働時間の上限が改正され、労働力の減少から起こる物流の諸問題)の対応へ向けて、業界横断で配送の効率化に取り組むなど、主にロジスティクスの領域でキャリアを重ねてきました。
EC事業部長に就任したのは2024年9月です。まったくの未経験ですから、先入観や固定観念がありません。サプライチェーン全般を通した業界のあるべき姿、予測される市場の変化に基づき、上位の戦略を立て、EC部門に必要な機能を整理してきました。今後は中期経営計画の実現に向けて、本格的に事業をドライブさせていくフェーズです。
井東氏:家電業界で長く勤務し、前職でECとバイヤーを経験しました。2023年にビックカメラに入社し、以来EC事業部に在籍しています。現在のミッションは、「ビックカメラ・ドットコム」の商品ページのリッチ化です。画像の点数やテキストの内容や分量が適切に表示されるよう管理しています。
——御社のECにおける戦略とは、どのようなものですか?
畑中氏:日本のEC市場は年率7〜8%程度で成長しています。特にモバイルだけ見れば、10〜13%と、極めて高い成長率で推移しています。世代間のニーズを考慮しながら、多様なお客様に対して、モバイルでの高度なユーザビリティを提供していくことが大切です。
私たちの強みは、眼の前でお客様に接し、直に声を聞いてきたことです。プラットフォーマーにはないリアルな体験を持っており、だからこそお客様に近い位置で価値提供ができると考えています。
量販店は安さが注目されますが、価値はそれだけではありません。お客様にとって本当の利便性、使いやすさとは何なのか?よりよい顧客体験の追求で、お客様を引き寄せることができると信じています。UI/UXの向上が、私たちの最上位の戦略です。
SKU200万から400万へ──商品点数の急拡大に挑んだ理由

——よりよい顧客体験は、どのように実現されるのでしょうか?
畑中氏:私は着任以来、アナリスト集団を強化してきました。お客様の動向は1日単位で変化しています。サイトから緻密にニーズを分析し、即座に打ち手が描ける組織が必要です。
一方、デジタルだけでは、店舗のようにお客様を直接見ることができないので、複雑に考えすぎてしまう傾向があります。顧客体験の根本は「欲しいものが見つかる」というシンプルなものです。必要とする商品が売り場にあり、価格に納得できて、望んだ時間と場所で受け取れる。一連の体験が、お客様の高い満足度につながります。
そのための戦術のひとつとして、直近2年で「ビックカメラ・ドットコム」のSKUを約200万から約400万へ倍増させました。
Lazuli PDP導入の背景──人海戦術では限界があった
——商品数が一気に200万も増えたのですか!?すごいですね!
畑中氏:400万と言えば、大きな数字に見えるかもしれません。しかし、お客様にとっては、全体の商品数より「そこに自分の欲しいものがあるか」が重要です。
アイテム数は大きく伸長させることができましたが、ECでは商品情報がなければ、お客様は商品を見つけられません。見つけられなければ、品ぞろえはないのと同じです。そのために人手をかけ手作業で商品情報の入力を進めてきましたが、すべての情報をそろえるのは難しく、商品拡大のスピードに対応できていませんでした。
井東氏:主に拡大してきた非家電部門の商品は、仕入先から十分な商品情報を得ることが難しい状況でした。アルバイトを40人ほど雇用して、メーカーに直接問い合わせるなどして、まずはとにかく掲載する商品数を増やすために情報を拡充してきましたが、人海戦術ではとても追いつきません。そこで、Lazuli PDPを導入しました。
畑中氏:Lazuli PDPを選んだ決め手は、国内実績が豊富だったことですね。ニトリさんやベイシアさんのように大規模な小売企業が、Lazuli PDPを利用しています。同じようなユーザーを持つ企業で実績があったのは、大きな評価ポイントになりました。
——Lazuli PDPをご導入いただいて、まだ間がありませんが、感じている効果はありますか?
井東氏:商品情報の入力作業は、人力で行っていたときと比べ、一部の面をカットして測った数字にはなりますが、生産性が百倍程度にはなっていると思います。

畑中氏:現状ではまだLazuli PDPのデータをWebサイトへ反映できていませんが、PoCを行ったことで、既存のデータの不足や不整合など、私たちが対応するべき課題が見えてきました。いくつかの点を解消すれば、実装までは早いと感じています。
ECを“家族のような存在”に──日常的接点を生む発想とは
——EC事業部の今後の展望を教えてください。
畑中氏:2025年からの中期経営計画では、ECの大きな成長が求められています。グループ全体のEC売上目標は、2029年8月期の計画で1,602億円、2024年比157%と、非常に高い数字です。
ECは物流と密接に連動しており、バランスを欠けば全体の効率が悪化するリスクがあります。そのため、まずは物流を強化したうえで、2027年以降にECを飛躍的に成長させる計画を立てています。
今は、ストレスなく「欲しいものが見つかる」を徹底的に追求し、基盤を構築する期間です。店舗の販売員が、お客様のリクエストをお聞きしてご案内するような、シンプルなサービスをデジタルで表現しなければなりません。キーワードで検索すれば、スムーズに目的の商品がヒットしたり、チャットボットで適切なご案内ができる環境をつくるには、商品情報の充実が必須です。
EC事業部のスローガンとしては、「お客様にとって家族のような存在のECサイトになる」を掲げています。朝起きて開く天気予報アプリや、外出先で確認する地図アプリのように、お客様が購買を意識しない時でも、日常的に接点を持てる存在になりたいのです。
ならば、ビックカメラのアプリで天気予報や地図が見られても良いはずです。他にもニュースや株価をチェックしたり、ゲームで遊べるなど、複合的にユーザビリティを向上する方法はあると思うのです。何でもやるという意味ではなく、ビックカメラのお客様が求めることを、見極めたうえで、家族のように寄り添って多様な価値を提供していきたいと考えています。
——幅広い施策の実行に集中していただけるよう、その最も根幹となる商品マスタの整備、商品情報の拡充という点で、引き続きご支援できればと思います。
畑中氏:今後の人口動態の変化、労働力人口の減少が見込まれる中では、コーチングコストも大きな経営課題です。
これまで、アルバイトのスタッフが商品情報を調べるために、連絡先を指示したり、コミュニケーションの仕方を教えたりと、社員も少なくない時間と労力を費やしていました。Lazuli PDPのようにオペレーションの多くの部分を代替する可能性があるソリューションは、こうしたコーチングコストの削減にも貢献します。社員は教える負担を手放し、生産性の高い仕事に集中することができます。
——ありがとうございます。ご期待に応えられるよう、しっかりとサポートさせていただきます。
株式会社ビックカメラ 公式企業サイト:https://www.biccamera.co.jp/
ビックカメラ・ドットコム:https://www.biccamera.com/bc/main/
Lazuli PDPについて:https://lazuli.ninja/product-data-platform/